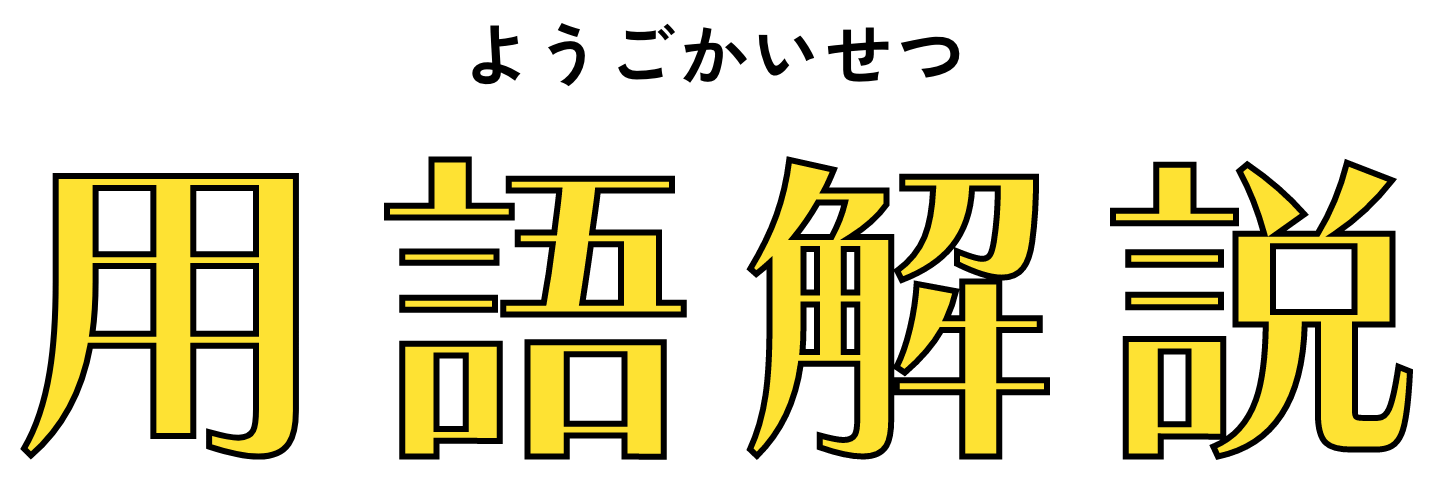もくぞうしゃかにょらいざぞう
木造釈迦如来坐像
国東市武蔵町成吉1089 圓明寺

もくぞうしゃかにょらいざぞう
木造釈迦如来坐像
国東市武蔵町成吉1089 圓明寺
仏教をはじめた釈迦【しゃか】は、のちに釈迦如来としてまつられました。この像は、右手を体の前でかざし、左手を膝の上に置いています。この手のかたちは「大丈夫、心配ない」という意味です。
釈迦(しゃか)
仏教をはじめた人で、もとの名前はゴータマ・シッダールタといいます。紀元前5世紀ごろのインドに「釈迦族」という貴族の王子で、きびしい修行の末、さとりをひらいて如来になりました。釈迦族出身の如来ですので、「釈迦如来」とよばれるようになりました。

-
寄木造【よせぎづくり】
寄木造(よせぎづくり)
仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

-
肉髻【にっけい】
肉髻(にっけい)
さとりをひらいた「如来」のからだの特徴のひとつです。頭の上にもりあがった大きなこぶのような部分のことをいいます。

-
釈迦【しゃか】
釈迦(しゃか)
仏教をはじめた人で、もとの名前はゴータマ・シッダールタといいます。紀元前5世紀ごろのインドに「釈迦族」という貴族の王子で、きびしい修行の末、さとりをひらいて如来になりました。釈迦族出身の如来ですので、「釈迦如来」とよばれるようになりました。

-
光背【こうはい】
光背(こうはい)
仏像の後には、板のようなものがついています。これは、光をあらわしたものです。仏教では、ブッダ(お釈迦さま)がさとりを開いた時、かがやきはじめたといいます。光背は、そのかがやきをあらわしたものです。ただ、明王は、怒りを示す炎をデザインしています。

-
衣文【えもん】
衣文(えもん)
仏像が着ている衣のシワのことです。衣のヒダといっていいかもしれませんが、いずれにしても衣を着た時にできるでこぼこです。

もっとくわしく
この像には、小さめの肉髻【にっけい】や、上半身に比べて下半身が小さめで、衣のしわ(衣文【えもん】)は曲線を多く使った複雑な表現がみられます。これらは、当時の中国の影響をうけたデザインで、こうしたデザインは鎌倉時代終わりから南北朝時代にかけてみられる特徴です。像高【ぞうこう】は62.5cmあり、ヒノキを用いた寄木造【よせぎづくり】の仏像です。なお、いくつかの材によってつくられていますが、その木の組み方も複雑で、上で紹介した時期に特徴的な構造です。なお、台座【だいざ】と光背【こうはい】には墨書【ぼくしょ】があり、後の時代につくられたことがわかります。
寄木造(よせぎづくり)
仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

肉髻(にっけい)
さとりをひらいた「如来」のからだの特徴のひとつです。頭の上にもりあがった大きなこぶのような部分のことをいいます。

光背(こうはい)
仏像の後には、板のようなものがついています。これは、光をあらわしたものです。仏教では、ブッダ(お釈迦さま)がさとりを開いた時、かがやきはじめたといいます。光背は、そのかがやきをあらわしたものです。ただ、明王は、怒りを示す炎をデザインしています。

衣文(えもん)
仏像が着ている衣のシワのことです。衣のヒダといっていいかもしれませんが、いずれにしても衣を着た時にできるでこぼこです。

-
指定年月日 令和3年3月2日 -
記号番号 彫第118号 -
種別 彫刻 -
所有者 圓明寺