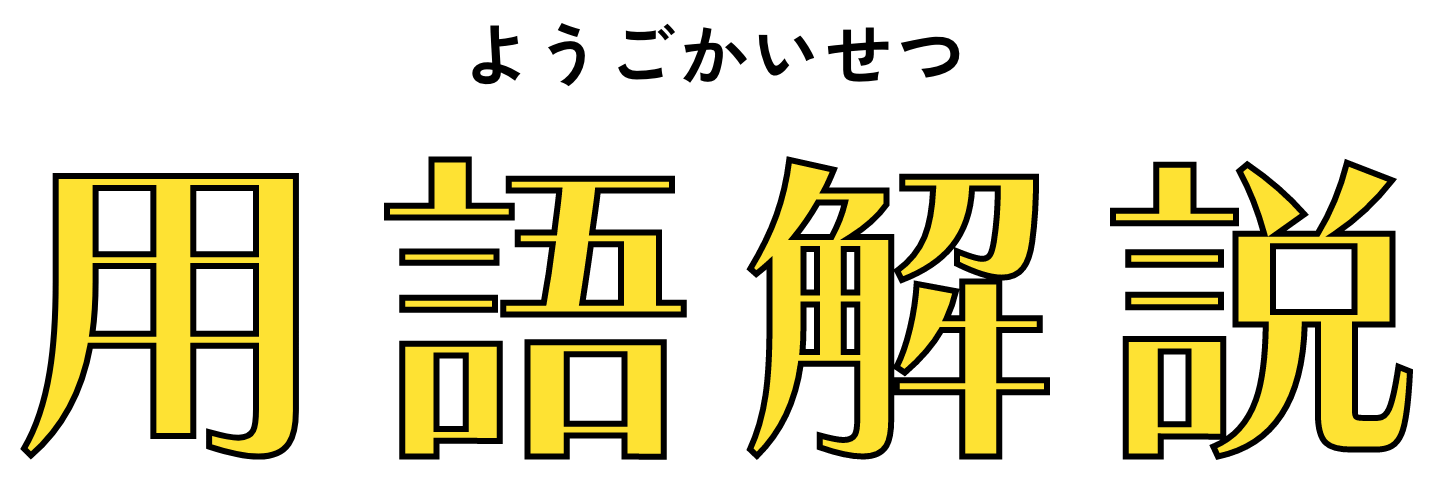県指定 有形文化財
もくぞうこんごうりきしりゅうぞう
木造金剛力士立像
宇佐市安心院町松本

県指定 有形文化財
もくぞうこんごうりきしりゅうぞう
木造金剛力士立像
宇佐市安心院町松本
宇佐市安心院町にある金剛力士像です。腰布のなびきなど、写実的につくられています。今は失われていますが、もともと水晶で作られた目玉がはめこまれていました。鎌倉時代につくられたと考えられます。
-
寄木造【よせぎづくり】
寄木造(よせぎづくり)
仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

-
玉眼【ぎょくがん】
玉眼(ぎょくがん)
仏像をつくる時、人間のように眼が光るよう工夫された技術です。眼のかたちをくりぬき、裏側から水晶のレンズをいれます。レンズの裏側から黒目を描き、白い紙をいれてつくります。平安時代後半にうまれた技術です。

もっとくわしく
口を開いた方を阿形【あぎょう】、口を閉じた方を吽形【うんぎょう】といいます。像高【ぞうこう】は阿形227.5㎝、吽形220.0㎝です。いずれもクス材を使った寄木造【よせぎづくり】で、眼には玉眼【ぎょくがん】がはめられていましたが、現在は失われています。怒りの表情、筋肉が盛り上がる体、なびく腰裳【こしも】の表現など、写実的につくられています。鎌倉時代の後半期につくられたと考えられます。
寄木造(よせぎづくり)
仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

玉眼(ぎょくがん)
仏像をつくる時、人間のように眼が光るよう工夫された技術です。眼のかたちをくりぬき、裏側から水晶のレンズをいれます。レンズの裏側から黒目を描き、白い紙をいれてつくります。平安時代後半にうまれた技術です。

-
指定年月日 昭和32年3月26日 -
記号番号 彫第7号 -
種別 彫刻