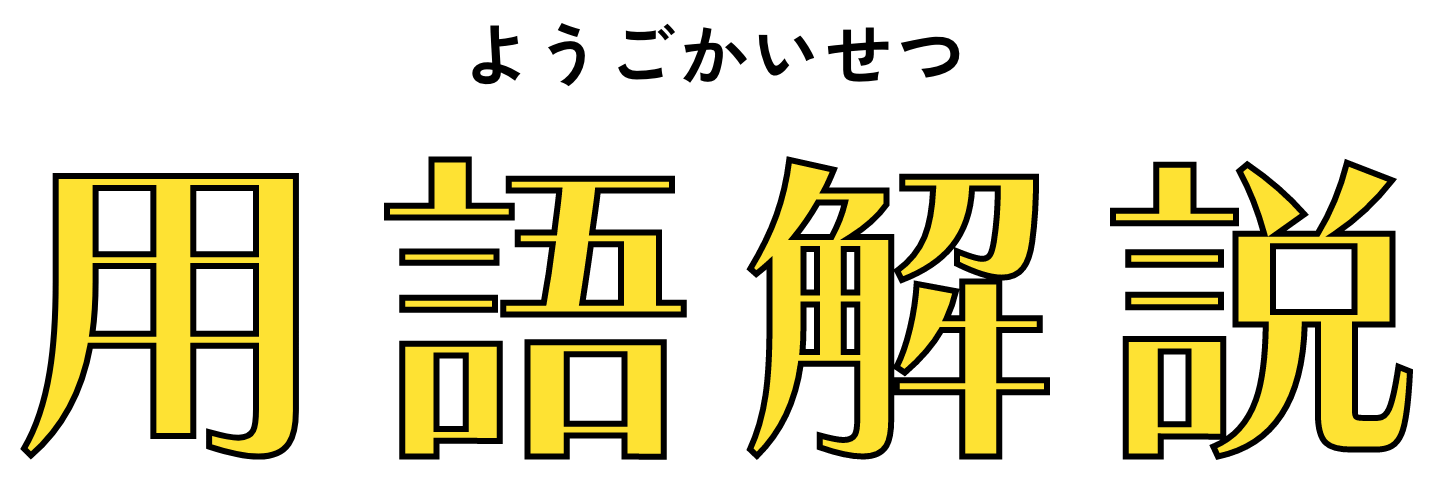もくぞうみあみだにょらいざぞう
木造阿弥陀如来坐像
宇佐市法鏡寺124 任聖寺

もくぞうみあみだにょらいざぞう
木造阿弥陀如来坐像
宇佐市法鏡寺124 任聖寺
小さな阿弥陀如来の像です。もとは宇佐八幡宮や弥勒寺【みろくじ】に仕えたお坊さんが住む坊のひとつである真乗坊【しんじょうぼう】にまつられていました。神仏習合【しんぶつしゅうごう】の様子を知ることができる仏像です。
神仏習合(しんぶつしゅうごう)
仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

-
螺髪【らほつ】
螺髪(らほつ)
髪の毛がとても長いことが、さとりをひらいた「如来」のからだの特徴のひとつです。長い髪の毛は、丸まってパンチパーマのようになっています、これを螺髪といいます。

-
寄木造【よせぎづくり】
寄木造(よせぎづくり)
仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

-
銘文【めいぶん】
銘文(めいぶん)
石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

-
神仏習合【しんぶつしゅうごう】
神仏習合(しんぶつしゅうごう)
仏は日本の神が姿を変えた存在とする考え。「習」という漢字には、「かさなる・かさねる」の意味があります。

もっとくわしく
像高【ぞうこう】は51.0㎝あります。ヒノキを用いた寄木造【よせぎづくり】の像で、像底【ぞうてい】に、「文□二年」という年号が記されています。小粒の螺髪【らほつ】におだやかな顔、なで肩で、全体におだやかな姿、こうしたデザインは平安時代後半の特徴です。すると、平安時代後半で「文□二年」にあたる年号は「文治二年(1186)」と考えられますが、この銘文【めいぶん】が制作に関するものかはっきりとしませんので、ここでは時代のみを記しました。
螺髪(らほつ)
髪の毛がとても長いことが、さとりをひらいた「如来」のからだの特徴のひとつです。長い髪の毛は、丸まってパンチパーマのようになっています、これを螺髪といいます。

寄木造(よせぎづくり)
仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

銘文(めいぶん)
石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

-
指定年月日 昭和44年3月22日 -
記号番号 彫第22号 -
種別 彫刻 -
所有者 任聖寺