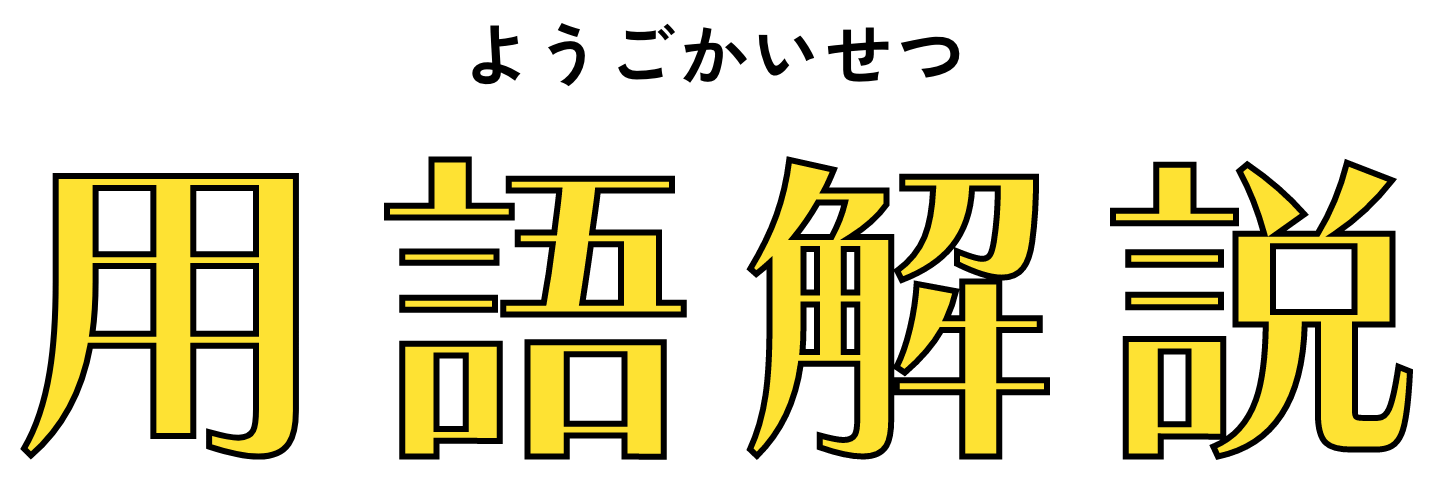もくぞうあみだにょらいざぞう
木造阿弥陀如来坐像
豊後大野市三重町赤嶺1461-3 市辺田八幡社

もくぞうあみだにょらいざぞう
木造阿弥陀如来坐像
豊後大野市三重町赤嶺1461-3 市辺田八幡社
高さ261.0㎝の巨大な阿弥陀如来坐像です。鎌倉時代につくられたと考えられます。大野川流域に残る巨像として注目される作品です。
-
寄木造【よせぎづくり】
寄木造(よせぎづくり)
仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

-
丈六【じょうろく】
丈六(じょうろく)
ブッダ(お釈迦さま)は、1丈6尺(約4.85m)だったといいます。そこで、仏像の大きさとして、1丈6尺、略して「丈六」が1つのきまりになりました。すわった場合は、半分の8尺(約2m40㎝以上)が「丈六」の仏像になります。

-
玉眼【ぎょくがん】
玉眼(ぎょくがん)
仏像をつくる時、人間のように眼が光るよう工夫された技術です。眼のかたちをくりぬき、裏側から水晶のレンズをいれます。レンズの裏側から黒目を描き、白い紙をいれてつくります。平安時代後半にうまれた技術です。

もっとくわしく
像高【ぞうこう】261.0㎝を測る丈六の阿弥陀如来坐像です。「丈六【じょうろく】」とは1丈6尺(約4.85m)を略したもので、釈迦の身長を表しています。この仏像は座っているため、その半分ほどの像高です。クス材を使った寄木造【よせぎづくり】で、眼には玉眼【ぎょくがん】がはめられ、仏像の表面には漆箔【うるしはく】が施されています。鎌倉時代末期の作と考えられますが、一部は江戸時代に補作されたものと思われます。大野川流域に残っている巨像の一つとして注目される作品です。
寄木造(よせぎづくり)
仏像を木でつくる時の制作技法で、全身をいくつもの部材にわけて制作するもの。

丈六(じょうろく)
ブッダ(お釈迦さま)は、1丈6尺(約4.85m)だったといいます。そこで、仏像の大きさとして、1丈6尺、略して「丈六」が1つのきまりになりました。すわった場合は、半分の8尺(約2m40㎝以上)が「丈六」の仏像になります。

玉眼(ぎょくがん)
仏像をつくる時、人間のように眼が光るよう工夫された技術です。眼のかたちをくりぬき、裏側から水晶のレンズをいれます。レンズの裏側から黒目を描き、白い紙をいれてつくります。平安時代後半にうまれた技術です。

-
指定年月日 昭和33年3月25日 -
記号番号 彫第9号 -
種別 彫刻 -
所有者 市辺田八幡社