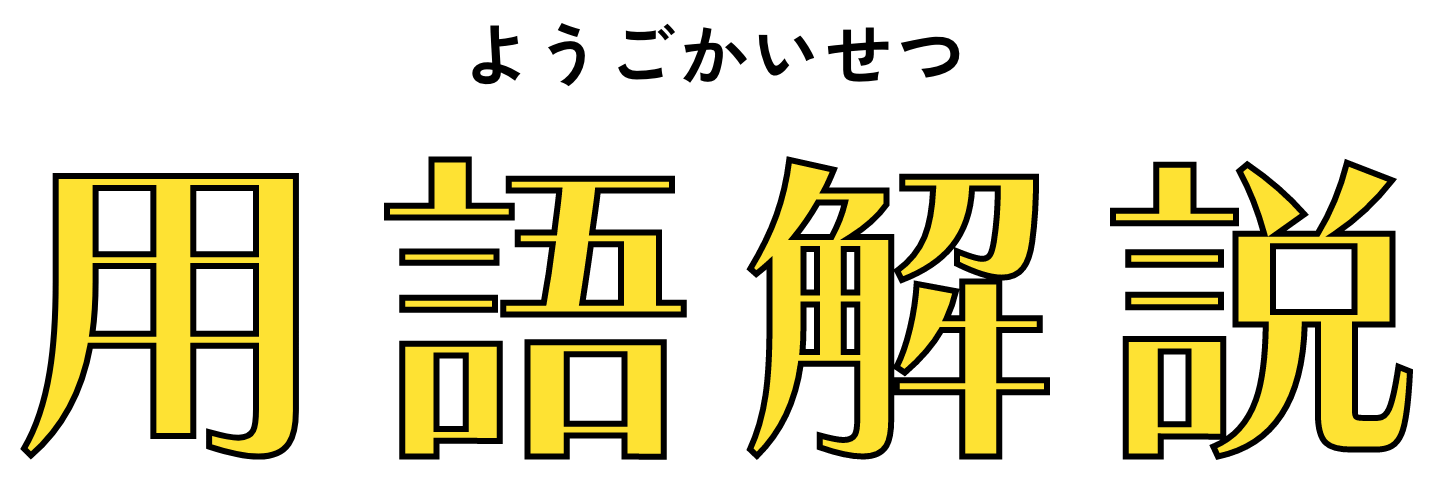県指定 有形文化財
うしゅくじんじゃわにぐち
烏宿神社鰐口
日田市大山町西大山5364 烏宿神社

県指定 有形文化財
うしゅくじんじゃわにぐち
烏宿神社鰐口
日田市大山町西大山5364 烏宿神社
鰐口【わにぐち】とは、お寺や神社につりさげて打ち鳴らす道具です。銘文【めいぶん】から、室町時代に、文奥という人物が奉納し、さらに大蔵永家という武士が改めて奉納したことがわかります。
銘文(めいぶん)
石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

-
銘文【めいぶん】
銘文(めいぶん)
石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

もっとくわしく
鰐口【わにぐち】は、仏堂や神社社殿に吊り下げて打ち鳴らした仏具の一種です。「烏宿神社鰐口」は、銘文【めいぶん】から、室町時代の応永6年(1399)に「文奥」という人物が「大山河内烏宿五社」へ奉納したことがわかります。さらに別の銘文には、永正2年(1505)に日田郡司職大蔵永家から改めて奉納されたことが書かれています。総径は20.0cmあり、片面交替式の2耳をつけた両面同文品で、各面を紐帯により3区に分け、撞座区の内部にはさらに素文円形の撞座をもっています。鋳あがりが良好で、二耳や両ロ角の突出も比較的控えめにつくられるなど古様な形姿をとどめています。
銘文(めいぶん)
石塔や仏像の内部、工芸品などに記された、年号や制作者の名前、その文化財をつくる理由や願いを記した文章(願文【がんもん】)などをいいます。

-
指定年月日 昭和51年3月30日 -
記号番号 工第51号 -
種別 工芸品 -
所有者 烏宿神社